9月19日(金)に、第61次静教組養護教員部研究集会(静養研)が行われ、単組・支部から養護教員、代表者合わせて88人が参加しました



静教組を代表して、赤池 中央執行委員長からは次のような挨拶がありました

子どもたちの多様な学びはすべての学校で行われるべきであり、すべての子どもたちの多様な学びに寄り添うべき…静教組では、校内教育支援センターの充実を求める
校内教育支援センターに求める機能は、養護教員が担っていないか…全国では半数の学校で設置されていないため、養護教員の負担となっており、養護教員の複数配置、校内教育支援センターの設置は急務
専門部活動の主な目的は、交流をすること…エリア制、県教研の教研ネットへの将来的な移行により、さらなる交流を深めていただきたい
講演では、小林朋子 静岡大学教授から、
災害時における子どものケアのありかた
をテーマに、次のような内容の講話をいただきました


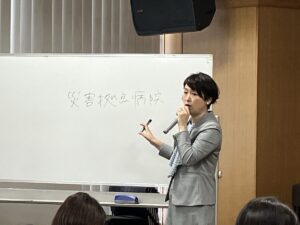
学校保健安全法第26条からの「リスクマネジメント」と「クライシスマネジメント」
子どもたちが学校にいるときに災害が起きたら、保護者との連絡をどうとるか…学校代表番号と「171」
地震や津波から逃げられても、熱中症で倒れる危険性…猛暑の中で災害が起きたときに、学校でつかえる水は?グラウンドや屋上に避難したときの日陰は?
子どもが通学途中(特に下校時)に危機が発生した場合はどう対応するか
学校で災害が起きたときに、目の前の子どもたちに集中できるよう、自身の家族との連絡をとれる方法を考えておく
生き残っているから、「こころのケア」ができる…喪失反応を減らす
PTSR(ストレス反応)は誰にでも起こるので、「こころのケア」が必要







続いて、後藤 静教組養護教員部長から、次の項目について基調報告を行いました

子どもをとりまく現状
いじめ・不登校・人権問題の複雑化・深刻化
学校保健をとりまく現状
集団フッ化物洗口・塗布
性教育・性の多様化
養護教員の配置と働き方
養護教員の標準的な職務
また、分科会での協力者として、歴代養護教員部長が紹介されました

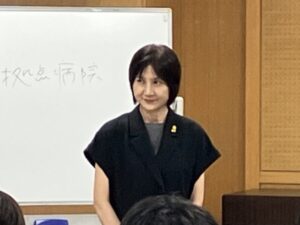
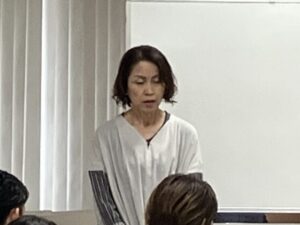

その後、分科会会場にわかれ、参加者同士で会話しながら昼食をとり、午後の協議に向けた関係づくりができました
分科会では、それぞれのテーマについて意見交換が行われました
第1分科会 子どもたちをとりまく問題






第2分科会 集団フッ化物洗口・塗布の課題






第3分科会 性教育・性の多様性へのとりくみ






第4分科会 養護教員の標準的職務について考える






真剣な表情での意見交換の中でも、時折笑顔もみられ、地区の垣根を超えた「語り合い」が多くみられました
養護教員をとりまく課題は多くありますが、ともにとりくむ仲間が県内各地にいます
今後も養護教員をとりまく課題解決や子どもたちの健康権に関する改善に向けて、養護教員部としてとりくんでまいります


