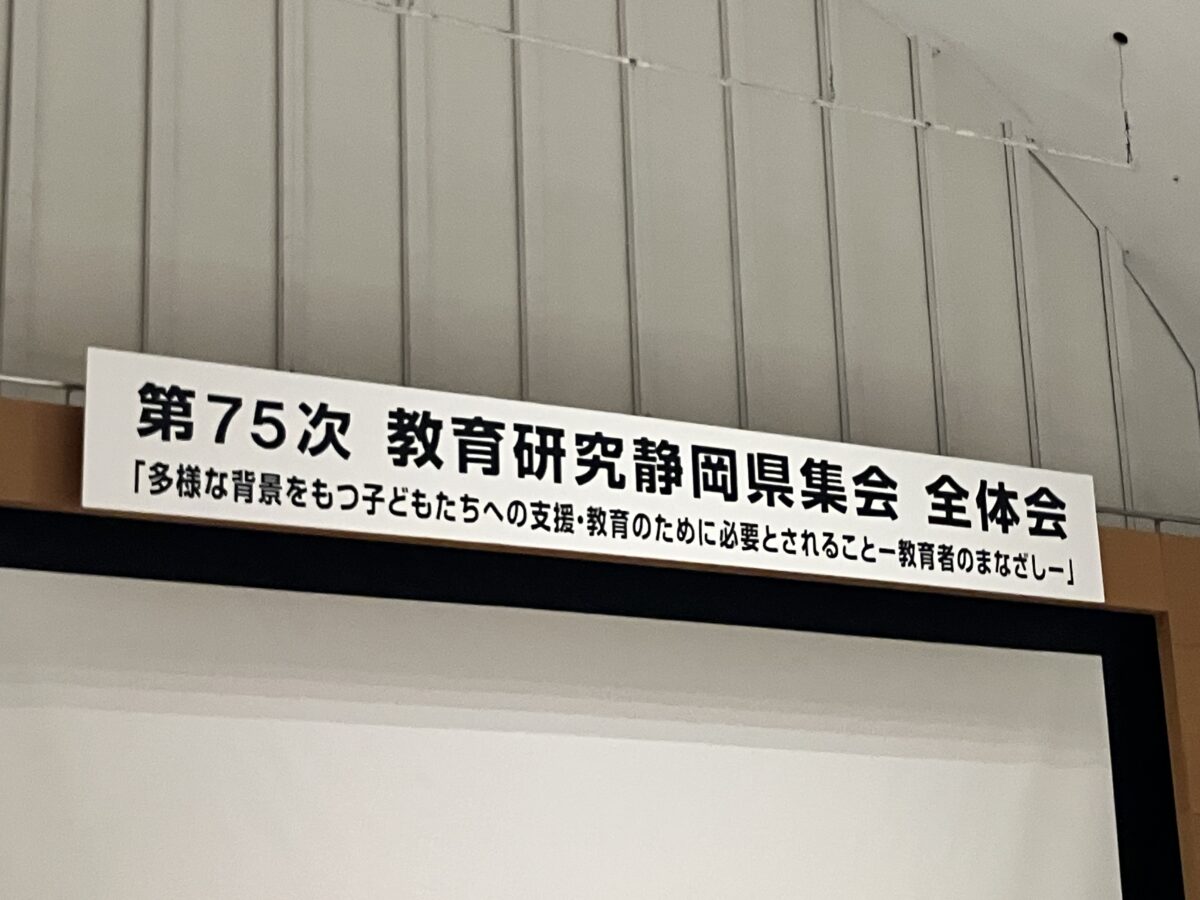9月6日(土)に、第75次教育研究静岡県集会全体会がグランシップで行われ、県内各地より200人を超える組合員が集まりました

また、多くの方にオンラインで参加いただきました(通知でお渡しした二次元コードに不備があり、ご参加できなかった方がいらっしゃいました。大変失礼いたしました。現在は、ブログ「第75次県教研全体会」でご覧いただけます。また、11月1日まではオンデマンド配信を行いますので、ぜひご覧ください)

会に先立ち、赤池 中央執行委員長より、以下のような内容で挨拶を行いました
今年度より「教育研究ネットワーク」という新たな研究推進体制をスタートさせ、『語り合う』ことを大切に、「教育研究活動の日常化」を図りたい
「排外主義」の広がりは国際平和や国際協調を脅かすものとなることから、どのような学びが必要か、そのためにどのような条件整備が必要か考えたい
不登校児童生徒が増加する中、学びの多様化学校の新設やフリースクールへの財政支援を行っているが、すべての子どもたちの多様な学びに寄り添う学校教育のあり方を追求する必要がある
現在、学習指導要領の改訂に向け協議がすすめられているが、学習内容や学習方法を抜本的に見直し、学校で学び合うことの楽しさを味わうことができるカリキュラムを構築すべき
来賓を代表して、長澤 静岡県PTA連絡協議会会長より、現在多様性への対応が求められる中、先生方に尽力いただけていることへの感謝などについてご挨拶をいただきました

講演では、鎌塚優子 静岡大学教授より
多様な背景をもつ子どもたちへの支援・教育のために必要とされること~教育者のまなざし~
というテーマで講演をいただきました





小中学校における不登校の状況、外国にルーツをもつ子どもの増加
医療的ケア児の増加がしている中、教員として理解しておきたい点
ヤングケアラーの実態と子どもの貧困・児童虐待(特に心理的虐待)の様子
教室で見える「子どもたちの多様性」について、背景をどれだけ想像できるか
「価値観の多様化」に対する教育者の視点
教育者として大切にしたい「子ども理解」の姿勢
「人権感覚」が子どもの教育支援の根底を支える
人権感覚は、複数の要因(教育、社会体験、家庭環境、メディア等)によって醸成される
人権と世代間ギャップの深いかかわり…安心・安全な職場環境が、児童生徒にとっての安心・安全な学校環境につながる
魅力ある組織をどうつくるか…チームで働くために必要な『力』
「メルティング社会」から「サラダボウル社会」へ…一人一人の個性の違いが尊重される社会
学校はさまざまな多様性を受け入れる最前線…教職員は、次の社会を創りだす担い手を育てている
講演の途中では、鎌塚先生がステージを降り、インタビューを行ったり、体を使ったワークを行ったりしていただきました















参加者から、

「命・人権・教育についての研修が必要といわれる中、なかなか防災教育や教職員の人権について学ぶことがないが、今必要な研修は何か」
という質問が出され、鎌塚先生から丁寧に回答していただきました
最後に、鈴木 中央執行委員よりお礼を伝え、全体会が終了となりました

今回の講演では、子どもと向き合う教職員として大切にしなければならないことを改めて気づかされる内容でした
今回の講演をもとに、各分会での教育実践につなげていただくとともに、10月25日(土)に行われる第75次教育研究静岡県集会分科会につなげたいと思います