7月11日(金)に、第64次静教組事務職員部研究集会(静事研)が行われ、事務職員、委員長・支部長あわせて57人が参加しました


会の冒頭、赤池 中央執行委員長からは

小笠支部での組織拡大のとりくみについて、エリアでも同様なとりくみの広がりを期待したい
学校事務の勤務内容等について議論する時間がない中、本研究集会ではその議論ができる場である
ともに議論ができる仲間をさらに増やしてほしい
また、寺畑 静教組事務職員部長から、次の5点について 基調報告がされました

本来業務に専念できる環境(多忙な勤務の解消、36協定に基づいた労務管理)
共同学校事務室・学校事務センターの整備、職務内容の整理
事務職員の配置拡充
勤務条件の改善(5級、6級適用者の拡大、4級昇格年齢の適正化)
課題の共有と力量向上
そして、静事研への想いとして
自分以外の単組・支部の事務職員と「未来につながる繋がり」をつくってほしい
自分の耳で聞くこと…共同学校事務室が始まってから、他の単組・支部の情報が入らなくなった中、静事研は情報共有の場
自分の口で伝えること…仲間とともにたくさん話をしてほしい
参加している単組委員長や支部長にも事務職員の課題を知ってもらい、今後の条件改善につなげていきたい
という話も伝えました
続いて、政令市を巡る情勢について、原 静清教組事務職員部長、鈴木 浜松教組事務職員部長から報告がありました


給食費の公会計化によりかえって業務負担が増えていること、統合型校務支援システムが導入され混乱を生じているもののペーパーレス化が期待できること等、静岡市、浜松市の情勢を共有しました
講演では、和田 公務労協副事務局長から、2つのテーマに沿って以下のような内容を伝えていただきました

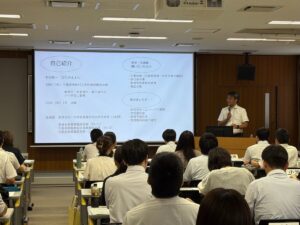
「今後の事務職員の職務のあり方」
“事務をつかさどる”と示されているが、他の職種と学校事務職員の職務の境目がわかりにくい
事務職員の職務を守っていくためには予算を獲得していく必要がある、静教組だからできる予算の取り方があるはず
学校事務という職がAIにとられないよう、とりくんでいただきたい
個人的には、今後、教員の事務をいかに担うかが必要だと考えるが、そのためには事務職員の労働条件改善に向けてとりくむことが必要
「人勧期のとりくみと公務員をとりまく情勢」
昨年の人事院勧告で、初任給が大幅引き上げられた一方、中堅・ベテラン層の賃上げがわずかだったことに、公務労協に対したくさんの批判意見が寄せられている
人事院給与局長は「若年層以外の職員についても職務に応じた給与の改善をすすめていく」と回答していることから期待をしていきたい
連合の春闘調査や経団連、日経新聞などの結果を見ると、今年度の賃上げ率は昨年度並みと考えられる
人事行政諮問会議最終提言には「官民比較する対象の企業規模を現行の50人から少なくとも100人以上に戻すべき」等が示されたことは妥当だが、「政策企画・高度調整の本府省職員を1000人以上企業と比較」にするのは疑問点が多い
退職手当の見直しが2027年4月に見解表明、政府方針の決定が行われると推察
60歳前後の給与カーブの連続性の確保のために、2028~2029年ころまでには考えが示されると推察が、大きな課題
昼食後、「今後の事務職員部の職務のあり方」をテーマとして、分散会が行われました
討議では、
共同学校事務室・学校事務センター等の現状と課題
多忙な勤務の現状とその解消に向けた方策
学校運営参画にかかる諸課題
学校事務再編の実施状況
等を柱に熱心な議論がされました
<分散会A>






<分散会B>






<分散会C>






<分散会D>






<分散会E>






<分散会F>






事務職員部の取組や活動内容について、各単組・支部から様々な意見が出されました
ここで話し合われた内容をもとに、今後の事務職員部の活動をすすめていきます


