
第1791号2008年6月25日
トップ会談 子どもたちのために手をとりあって
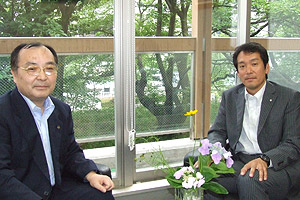
6月11日(水)、静岡県PTA連絡協議会の鈴木茂之会長と加藤典男委員長とのトップ会談が静教組委員長室にて行われました。意見交換を通して、子どもたちの健やかな成長という同じ目的のために、連携していくことを確認しました。以下、会談の要旨を紹介します。
加藤委員長:
報道される様々の事件や子どもたちの様子から背景に危機感を覚えるのですが、どのように捉えていらっしゃいますか。
鈴木会長:
秋葉原の事件でも茨城の事件にしても、自己肯定感を得ないままで大人になってしまったと感じます。親が自己満足のために愛情を注いでしまったのかもしれません。そういう育ち方をしたことが衝動的な行動になったのだと思います。
加藤:
家庭における育ち方や愛情の注ぎ方の問題ですね。家庭環境や社会環境の変化に危機感を覚えます。それに対し何ができるかということなのですが、県PTAの「ごはんだよ 全員集合!」のとりくみについて、やられてみて様子はいかがでしたか。
鈴木:
今まで県PTAの単独のとりくみがなかったので、何かを前向きにやってみたいという気持ちがありました。発信することで、そこから見えることをさぐりたいと思いました。アンケートには、様々な反応がありました。言えることは、保護者がその気になることで大人も子どももよくなるということです。今後も保護者を啓発する地道なとりくみを続けていきます。
加藤:
保護者を啓発していく一つの方策だったわけですね。教育条件整備をすすめ、ゆき届いた教育環境を実現することが必要だと思うのですが、それについてはどのようにお考えですか。
鈴木:
文科省が財務省に対して教育予算増額を求めていますが不十分です。OECDの中での日本の教育予算はとても低いと思います。国民みんなが必要だとわかっていることに対して予算をつぎこまず、先生や保護者、国民への負担を強いています。やっていることがずれている気がします。
加藤:
学校も保護者も家庭も悩んでいるのに何とかしようとする方策がずれていますね。PTAと歩調を合わせられるところは、ぜひ一緒にとりくんでいきましょう。
鈴木:
同感です。PTAは、以前に比べてとりくむことが変わってきています。保護者の意識をかえていく必要があります。責任をもって主張ができる団体になりたいと思っています。
加藤:
私たちも教職員としてやることは責任をもってやります。その上で現実はこうですと言っていきたいと思います。子どもの社会性が大事になってきています。自己肯定感をもつことは、他人を大切にすることにつながります。それを育てないといけませんね。
鈴木:
相手がいて自分がいて、お互いに育っていくために相手の存在が必要ですね。子どもに社会性が欠けているということは、保護者も同じということです。社会性、メディアリテラシーといった今の保護者に足りないものを伝え続けていくことも現在のPTAの大事な役目です。
加藤:
教職員組合もPTAと有機的につながる関係でありたいと思います。PTAと力を合わせることができれば厚みが出ます。子どもたちのために一緒にできることを数多く探していきましょう。

